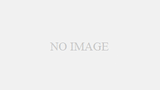大地震・津波などは周期的に発生しているという。
地球の年齢は40億年とか。それに比べれば人間のたかだか100年の寿命は限りなくゼロに近い。
地球にとっては100年周期で起こす地震も、地球の歴史・年齢からすれば極めて短い間隔であろう。
地球に寄生して生きる人間にとっては、地球の時間軸を考えて対応するべきでは?
災害に遭遇して、元への同じような形での復旧では、将来に同じ災害が起きる。
現在の災禍を如何に後世に引き継がないようにするか。地球の時間軸に合わせた考えで社会を築いていくべき。
(津波対策で防潮堤を造っても、実際に津波が来る頃には朽ち果てて役に立たないかもしれない。
複合施設、例えばリサイクル工場として継続するような形にする。)
一朝一夕に出来ることではなく、何世紀もかかるかもしれないが、同じ災害を繰り返す過ちをしているのでは、能(脳)が無い。
南海地震に遭遇した先人が、後世のために対策をした社会づくりをして、それを継続していれば、
今、南海地震や津波をそれほど怖れる必要はなかったのかもしれない。
過去の災害のその後の対応が、将来の地震に対する犠牲者・損害の危惧の一因になっている?
大きな地震が起きると(能登地震の如く)、電柱が倒れ、水道管は破壊され、長期間使用できない状態が続く。電気も水も一つの供給源から送っていると、途中で故障があれば被害が広範囲に及ぶ。
街を区切り、一定の地域でエネルギーや水等、全てを賄える体制を構築し、供給の部分的破損が広範囲に及ばないような体制。社会や生活のありようを考える。
(日本の人口は減少の一途を辿り、将来これまでの社会のありようでは立ち行かなくなるのは必定。)
費用と時間がかかろうが、長い目で見ればその方が災害発生時の被害を抑えられ、住民の安寧も得られるのでは?
災害は毎年のように必ず起きている。その規模も大きくなりつつあるような。
災害の対応は、当該自治体が行うことになっているらしい。
何時起きるか、起きないか、分からないような災害に個々の自治体が対応しているのでは、非効率。
災害が起きても被害の少ないような街づくりに力を注ぎ、災害が発生した際は、国が支援する。
復興時の街づくりも各自治体に任せていては、より良い方向での(国としての)統一した形はできない。災害対応のノウハウのようなものも国がまとめ蓄積し、活用する。
イタリアでは災害の対応は国が行うらしい。
国防のために防衛省があるように、国民の生命と財産を守るために防災省を創設し、国が主導し、災害時に二次被害を抑えるような準備・対応を行う。
能登地震のように発生から一か月たってようやく仮設住宅の(一部)入居では遅すぎる。
(前もって、国が組立式の仮設住宅をストックして、必要な所へ供給する。個別の自治体がその都度
行うのでは、時間もかかり、役目が済んだ後も解体して終わりでは、無駄。組立式なら、再度他の被災地に使用することが出来、効率的である。)
72時間以内に救えた命があっても、他方で災害関連死で命が失われるのでは何をしていることか。
災害が天災であっても二次災害は人災ではないか?
災害が起きてから用意するのでは遅い。災害は起きるものとして、国が即座に支援する体制を整える。その方が効率的であり、被害も抑えることが出来るのでは?災害対策のあり方を根本から変えるべき。
国と東京都は、東京が日本の首都であることの自覚と責任を持つべき。
もし東京が大地震に見舞われれば、日本全国に影響が及ぶ。
また、日本全国から東京へ災害援助隊が派遣されることになる。
生命や様々な危険をおかして援助に来る人々の負担を少なくすることは義務である。
そのためには、援助を必要とする人を出来るだけ少なくする必要がある。
一人暮らしの高齢者は地方にシェアハウスを建設、また空家の活用など行い、希望者はできるだけ移住してもらう。
戦後80年、戦時中は空襲から逃れるため、学童疎開が行われた、結果、後の東京大空襲で被害にあわずに済んだ学童も多かったはず。まだ起きないからと、のほほんとしているのは如何なものか。
大地震も黒船のようなもので、黒船が来ないと、変われないのでは誠に情けない。
国の機関の地方移転も併せて早急に取り組むべきではないか。